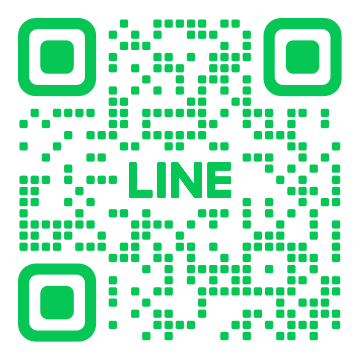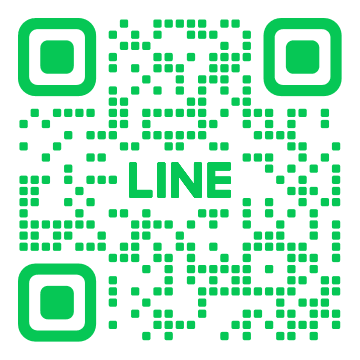ワインのOEM販売に必要な免許は?ワインエキスパートを有する行政書士が解説!
ワインや日本酒を、ワイナリー又は酒蔵に製造委託し、そのお酒を自社のお酒として販売する場合、必要となる免許は「酒類製造業免許」ではなく、「酒類販売業免許」です。 実際の例としては、ぶどう農家が育てたぶどうをワイナリーに製造委託する例が典型です。 日本で多い事例は契約栽培で、ワイナリーがぶどう農家からぶどうを買取り、ワイナリーが自社の商標と計算でワインを販売しますが、 日本でも新規参入のワイナリーが、まずはぶどう栽培から始め、醸造の工程を第三者に委託(OEM生産)、ワインを引き取り、自社のワインとして販売するOEM事例(プライベートブランド事例)が増えています。 本記事では、お酒のOEM販売(プライベートブランド販売)に必要な許可について、J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が解説いたします。

OEMの典型事例では「自己商標酒類卸売業免許」が必要
冒頭紹介した、生産(醸造工程)を委託する典型的な新規参入のワイナリーのOEM事例では「自己商標酒類卸売業免許」を必要とします。 「自己商標酒類卸売業免許」は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる免許で、申請時には「自らが開発した商標又は銘柄」であることが審査の対象とされます。 商標又は銘柄(ラベル)の写しのほか、自己の商標(銘柄)として登録済みである場合には、その登録済証の写しなどの提出を求められ場合もあります。 共同開発も認められています。
通常の卸売業の免許区分では、取り扱う酒類と卸の形態によって、免許区分が異なります。例えば洋酒の国内における卸売であれば、「洋酒卸売業免許」、 海外からの輸入による卸売であれば「輸出入酒類卸売業免許(うち輸入)」が必要です。一方、「自己商標酒類卸売業免許」については、法令上、申請が可能なお酒の種類に制限がありません。 日本酒でもワインでも申請が可能です。
自己商標酒類卸売業免許申請に必要な書類
自己商標による酒類卸売業免許の申請では、通常の卸売業免許における申請書類及び添付書類に加え、 自身が企画・開発したことを裏付ける書類、ラベルの案、製造が製造免許を受けた者に委託されことを疎明でき、かつ製造されたお酒の取引条件が明示された製造委託契約書、 加えて、販売予定先の酒販店から取得した取引承諾書が必要とされます。
| No. | 書類 |
|---|---|
| 1 | 商品の企画書または商標登録証(後者があれば前者不要) |
| 2 | ラベルの案 |
| 3 | 製造委託契約書 |
| 4 | 取引承諾書 |
OEMにおける一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許
「自己商標酒類卸売業免許」は卸業免許の一種です。従って、販売先は酒販店(一般酒類小売業、通信販売酒類小売業)に限定され、「自己商標酒類卸売業免許」だけでは、一般消費者や飲食店に販売することができません。

農家等事業者が「自己商標酒類卸売業免許」によって、OEMで製造したワイン等のお酒を、酒販店への卸売ではなく、一般消費者や飲食店に販売する場合には、「一般酒類小売業免許」又は「通信販売酒類小売業免許」を必要とします。 前者は取り扱い可能なお酒に制限がない一方で販売可能な地域が単一都道府県に販売が限定され、後者は販売方法が通信販売に限定され、かつ取り扱い可能なお酒に制限がありますが、全国への販売が可能な免許です。 両免許区分の詳細な違いについては、私の下記の記事をご覧ください。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いまとめ
解説を読んでいただき、ありがとうございました。 酒類販売免許はわかりにくく、とくに委託製造、OEM販売では悩まれる方も多いと思います。 行政書士事務所Crenlyでは、本稿で紹介した委託製造、OEM販売を含む、 酒類販売業免許の相談に無料で応じています!代表はJ.S.A.ワインエキスパートも有しており、ワインの専門です。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせください! また、ご要望と難易度に応じて、代表と同じくJ.S.A.ワインエキスパートを有する提携先の女性の行政書士と(単独受任時と変わらない価格で)共同受任することも可能です。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「お酒に関する情報」
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori