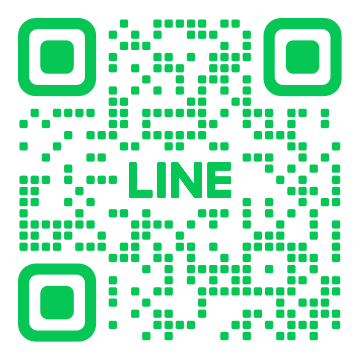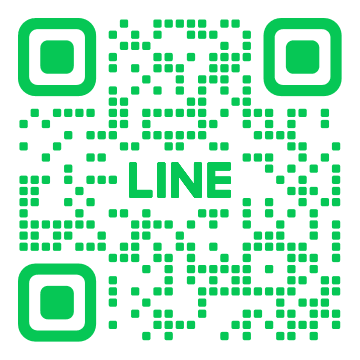イベント会場でワインやお酒を販売を販売する方法!
ブログをご覧いただきありがとうございます。 イベント会場や催し物(臨時販売場)で期間限定でお酒を販売する場合、「期限付酒類小売業免許」の届出又は申請が必要となるケースがあります。 本記事では、どのような状況で免許が必要になるのか、またその取得方法や必要な手続き、イベント終了後の報告義務まで、 J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が解説いたします。

期限付酒類小売業免許とは?
期限付酒類小売業免許とは、 短期間のイベントや催し物(臨時販売場)で、期間限定でワインや日本酒など酒類を小売販売する際に必要な免許です。
- 免許が必要となるケース:
・店舗内の一画で期間限定イベントを開催し、地方の地酒やワインなどを持ち帰り用で販売する場合
・お祭りや縁日で、缶ビールや缶チューハイなどを開封せずに販売する場合 - 免許が不要なケース:
・イベント会場で、その場で飲む目的でお酒をグラスに注いで提供する場合
また、この免許はすでに酒類製造業者や酒類販売業者としての免許を持つ事業者のみが取得可能です。
免許取得の手続き 「届出」と「申請」
期限付酒類小売業免許の取得方法には大きく分けて「届出」と「申請」の2種類があります。 それぞれの手続き方法と提出期限は以下の通りです。
届出の手続き
下記の条件をすべて満たしている場合、10日前に「届出」するだけで免許が取得できます。
- 申請者が免許を受けた酒類製造者または酒類販売業者であること
- 酒類の小売り目的が、特売又は在庫処分に当たらない
- イベントの開催期間又は開催期日が、あらかじめ定めらている
- イベントの主催者との契約等により、販売場の設置場所が特定されている
- 前1ヶ月以内に同一場所で販売場を開設するための届出を行っていない
- イベント等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内
- イベントの開催期間又は開催期日が、客観的に明確であること
- 販売する酒類の範囲が、既に免許を受けている酒類の品目と同じである
- イベント会場の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない
1,2,3,4の要件を1つでも満たしていない場合は、期限付酒類小売業免許の「届出」も「申請」もできません。 1,2,3,4の要件を全て満たすも、5,6,7,8,9の要件のどれかを満たせない場合は、「届出」ではなく「申請」によって 期限付酒類小売業免許の取得が可能な場合があります。なお、「申請」は2週間前までに 行う必要があり、「届出」とは違って不許可となる場合があります。 これをフロチャートにすると次の通りです。

イベント会場における酒類の販売管理者
イベント会場(臨時販売場)で酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。 選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に 「酒類販売管理者選任届出書」を提出することが義務付けられます。
イベント終了後(臨時販売終了後)に提出する書類
イベント会場での販売の終了後(臨時販売場の開設期間終了後)、 次の2点の書類を期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出します。
- 酒類の販売数量等報告書
- 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書
まとめ
解説を読んでいただき、ありがとうございました。 酒類販売免許はわかりにくく、悩まれる方も多いと思います。 行政書士事務所Crenlyでは、本稿で紹介した期限付酒類小売業免許を含む、 酒類販売業免許の相談に無料で応じています!代表はJ.S.A.ワインエキスパートも有しており、ワインの専門です。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせください! また、ご要望に応じて、代表と同じくJ.S.A.ワインエキスパートを有する提携先の女性の行政書士と(単独受任時と変わらない価格で)共同受任することも可能です。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「お酒に関する情報」
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori