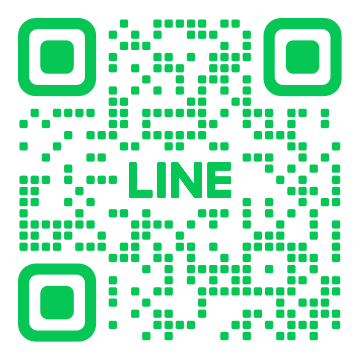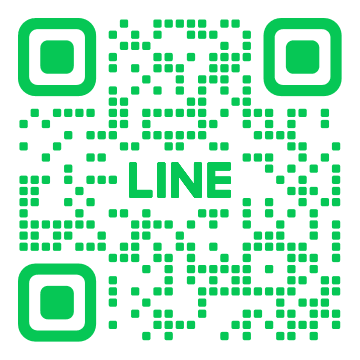一般酒類小売業免許における需給調整要件
ブログをご覧いただきありがとうございます。本稿では一般酒類小売業免許の4つの要件のうち、需給調整要件についてJ.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。

需給調整要件の根拠条文と背景
需給調整要件の根拠条文は酒税法10条11号です。下記に本文を引用します。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
出所:酒税法10条11号
11号に該当する場合は許可しないとの本文なので、このような書き方になっています。前段の『酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため』とは、新たに販売業免許を与えることで、その地域や全国の酒類の需給バランスが崩れ、販売の混乱を招き、既存の酒類販売業者の経営が不安定になり、その結果として酒税の適切な徴収に悪影響を及ぼすと判断される場合を指します。ようは、全体の事業者数と競争環境を勘案して、新規の免許の付与を抑制しようという規定ですが、幸いなことに一般酒類小売業免許と通信販売小売り業免許には、現在この免許の数自体を抑制する規定は撤廃されています。
一般酒類小売業免許の需給調整要件
一般酒類小売業免許における10条11号の要件については、国税庁より法令解釈通達が示されておりますので、下記に一部を引用します。
- 次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。
- (1) 設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。
- (2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。
出所:国税庁、酒税法法令解釈通達
1点目は分かりやすいです。例えば大企業が、販売先を社員に限定したワインショップを作ることはできません。このケースでは価格が市場での小売り価格より安価となることが想定され、全体の需給に悪影響を与えるためです。酒類販売免許の申請書本体には申請の理由、次葉4には、酒類の予定販売先を記入する欄がありますが、それぞれから販売先を限定する趣旨が読み取れれば、不許可となる可能性が高くなります。
2点目につき、バーとワインショップは、同じ空間、会計、在庫、帳簿のもとで一体と経営することはできません。居酒屋と酒屋、キャバクラとワインショップの関係でも同様です。他方、実店舗では併設した事例が多いわけですが、これらの店舗では、両者の空間、会計、在庫、帳簿が全て明確に区分され、「国税局長において免許を付与等することについて支障がない」と認められたケースです。
酒税法の世界では、ワインショップにあるワインボトルは、販売前・小売り前のお酒であるのに対して、バー・居酒屋・キャバクラにおいてあるワインの未開栓のボトルは、既に小売された消費されるべきお酒と扱われ、全く別物です。これらが明確に区分されず、混然一体となる恐れがある場合は許可されません。ワインセラーはもちろんのこと、仕入れ先、レジも分ける必要があります。
通信販売酒類小売業免許の需給調整要件
通信販売酒類小売業免許の需給調整要件は、一般酒類小売業免許とは全く別の、同じ条文の解釈とは思えない規定になっております。下記に国税庁の解釈を引用します。
通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が次の場合には免許を付与等する。
- 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である製造者(以下この4において「特定製造者」という。)が製造、販売する酒類
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類 - 輸入酒類
出所:国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
輸入酒類には制限はありません。国産酒類については、課税移出数量(≒前年度の年間の出荷量)が3,000キロリットル未満の種類しか取り扱うことができません。また、3,000キロリットル未満であることを証明するために、酒類の製造者の発行する証明書を取得する必要があります。すなわち、生産者と接点がないと取得できません。通信販売酒類小売業免許は、元々国内の小規模な酒蔵やワイナリーの販売を促進させたいという政策的な意図により設けられた、一般酒類小売業免許よりわずかに要件(経営基礎要件)が緩和された免許区分ですので、その政策意図に沿い、このような要件があります。
ブログ記事をご覧いただき、ありがとうございました。本稿で紹介した需給調整要件以外の3つの要件については、下段のリンク先の記事をご覧頂ければと思います。 当事務所の相談料は無料です。LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori