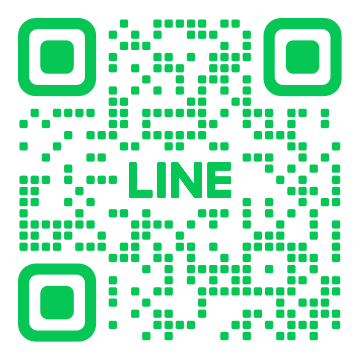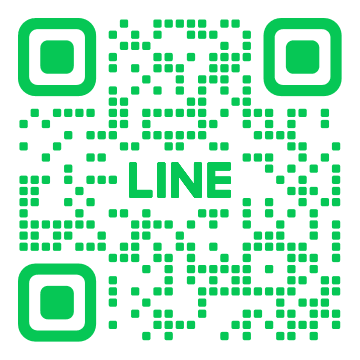一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
ブログをご覧いただきありがとうございます。本稿では、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いについて、 J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。

販売の手法と販売可能な地域の違い
通信販売酒類小売業免許では、酒類の店頭小売(いわゆるワインショップや酒店の業態)ができないことに加えて、 単一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできません(広く販売する必要がある)。 続いて、通信販売酒類小売業免許における通信販売の定義を確認します。
- 2つの都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として
- 商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し
- 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売方法
上記のように、通信販売酒類小売業免許の場合は、インターネット販売などを通じ、複数都道府県の消費者を対象にすることが前提となります。インターネットを通じた販売に限らず、カタログ、チラシを通じた販売も通信販売に含まれます。
ただし、県境を跨いインターネット、カタログ、チラシでの受注であっても、販売場近隣エリア(商圏)への販売であれば、 一般酒類小売業免許で対応できる場合もあります。このケースの場合は、税務署に事前相談することを要します。
一般酒類小売業免許の場合は、店頭販売を含めたさまざまな販売形態が認められ、 県境を跨がなければ、カタログその他通信販売による販売も可能です。 宅配ピザ等の業態で、チラシによって、近隣の地域に酒類を含めて販売しているケースがあると思いますが、 このケースが本件に該当します。
扱える酒類の違い
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とでは、扱える酒類にも違いがあり、 一般酒類小売業免許で扱える酒類に制限がない一方で、通信販売酒類小売業免許では扱える酒類の範囲に制限があります。 具体的には、次の通りの制限があります。
- 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ 発行年月日の属する会計年度の前年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、 全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」)が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、 かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。 - 輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限なし
輸入のワイン等輸入酒類を扱う場合に制限はないのですが、国産酒類を扱う場合には、 課税移出数量が3,000キロリットル未満に限定され、かつ、 3,000kℓ未満の証明書を生産者から取得する必要があります(下記)。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の要件の違い
経営基礎要件 – 人的要件
酒類販売免許には4つの要件が必要とされます。人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つです。 人的要件と場所的要件に違いはありません。需給調整要件については、 前述の国産酒類に係る3,000kl制限が要件そのもので、一般酒類小売業免許との比較では 要件がより厳しいとも言えます。
残った経営基礎要件(うち人的要件)については、 一般酒類小売業免許と比較すると、通信販売酒類小売業免許の方が少し緩和されています。 下記に手引きにおける両者の原文を引用します。本文の要件はほぼ同じですが、その下の解釈に違いがあり、 一般酒類小売業免許ではやや厳しい解釈が示され、通信販売酒類小売業免許ではそのような厳しい解釈が示されておりません (よって本文を自然に解釈すればよい)。


一般酒類小売業免許の経営基礎要件についてはこちらの記事で詳しく論じていますので、 ご覧になってみてください。
一般酒類小売業免許における経営基礎要件20歳未満の者の飲酒防止に関する表示
通信販売酒類小売業免許であれ、1つの都道府県内に販売地域を限定した一般酒類小売業免許による通信販売であれ、通信販売による場合は、20歳未満の者の酒類を販売しない旨の表示他、販売管理体制の構築は極めて重要です。 また、お酒に限った規制ではありませんが、通信販売による販売では、特定商取引に関する法律に準拠した販売方法とすることも重要です。 申請書においても、実際のホームページ等の媒体でそのような措置をとる予定であることを、添付書類を通じて疎明する必要があります。
ブログ記事をご覧いただき、ありがとうございました。 当事務所では一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許双方の初期的な要件の判断を含めた相談に無料で応じています。 私はワインショップを開けるのだろうか? ワインを通販できるのだろうか? と疑問を持たれている方、 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法(第10条10号)
- 特定商品取引に関する法律
- 20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori