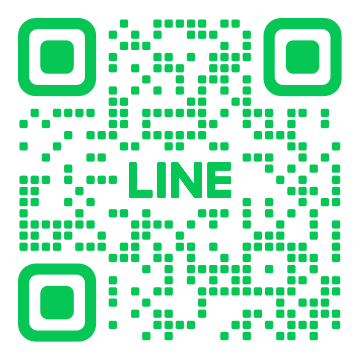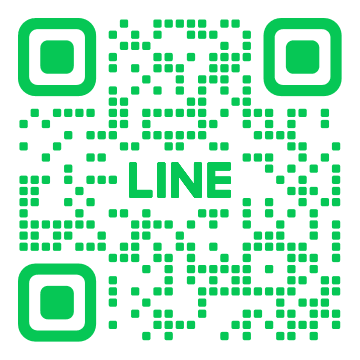一般酒類小売業免許における場所的要件
ブログをご覧いただきありがとうございます。本稿ではワインショップ等の一般酒類小売業免許の4つの要件のうち、苦労する方も多い場所的要件について、J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。

一般酒類小売業免許における店舗の考え方
こちらの記事でも簡単に触れましたが、 はじめに一般酒類小売業免許における店舗の考え方について整理します。酒類の小売業と言うと、酒屋のように店舗をイメージされる方が多いと思いますが、税法上は店舗ではなく、販売場と呼ばれ、かつ販売場には最終消費者の訪問を想定していない事務所が含まれます。店舗を持たない事務所のみの開業が可能ということです。
前者の最終消費者が訪れる店舗は、ワインショップや酒屋そのものです。他方、後者の業態としては、例えば、知り合いの最終消費者からメールや電話で注文を受けて、郵送で届ける業態や、販売場近隣の飲食店に対して、事務所から(正確には事務所に隣接する倉庫より)ワイン等酒類を納品する業態です。これらのビジネスモデルであれば、事務所のみで可能、店舗は不要です。
一般酒類小売業免許における免許の対象
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許で共通ですが、酒類販売における免許は、 事業者(申請者)に対して与えられるのではなく、1つ1つの販売場に対して与えられます。 従って、同じ事業者が複数の店舗あるいは事務所を持つ場合は、それぞれに対して免許を取得する必要があります。下記に国税庁のQAから一部を引用します。
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
出所:国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」
「販売場ごと」とは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。
場所的要件
本題の場所的要件です。場所的要件は、酒税法の第10条9号に規定され、同解釈指針と国税庁の手引きで解釈されていますが、 第10条9号とその解釈では、販売場が料理店等「他の営業主体」と明確区分されていることについての記載が多い一方で、 (料理店等と隣接しない)販売場それ自体が備えるべき、面積や独立性に関わる要件については読み取りにくい書き方となっております。
面積
同じお酒が関係する許認可で、バーやスナックを規定する風俗営業法には、営業所と客室が備えるべき面積について規定がされている一方で、酒類販売業を規定する酒税法には面積についての規定がありません。よって具体的な数値基準なしに、販売場として機能するに足る面積さえであればよいということになります。
独立性・区分性
酒類販売業の申請実務では販売場自体に「独立性・区分性」が必要であると言われます。 この要件は2つの解釈から導かれると思います。1つ目は第10条9号から直接導く解釈です。すなわち、他の営業主体との関係で独立性を求められる以上、 他の営業主体と隣接していない場合であっても当然に販売場は独立性・区分性を備えなければならないという解釈です。 2つ目は販売場にて選任が求められている「酒類販売管理者」の制度趣旨からの解釈です。 すなわち、「酒類小売業者は、酒類の小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、 販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。」(国税庁のホームページ)とされていることから、 販売場は、当然に、酒類の適正な販売管理をするに必要な独立性と区分性を備えていなければならないという解釈です。 また、酒税法10条10号のいわゆる経営基礎要件においても、「酒類の適正な販売管理体制が構築」を求める解釈が国税庁より示されおります。
区画された店舗の全てが酒類の販売場たる店舗である場合、または、オフィスビルの部屋が全て販売場たる事務所である場合は、料理店等と同じ店舗内に酒販店がない限りは、独立性・区分性は特段問題になりません。 問題となることがあるのは、シェアオフィス、自宅の一室、自宅の一室の一部、広いオフィス空間の一部など、 販売場が明確に独立・区分されているとは言い難い事例です。 シェアオフィスにつき、個室のないシェアオフィスでは免許はとれませんが、個室であれば、独立性・区分性が問題になることはありません (建物所有者の同意の問題は残りますので、別の投稿で詳細に論じたいと思います)。 実際、個室のあるシェアオフィスで免許を取得した事例は多いです。 次に自宅の一室ですが、こちらも建物所有者(賃貸人)の同意の問題を横に置くと、 自宅の一室が全て販売場たる事務所である場合は独立性・区分性は原則問題なしとされます。 最もハードルが高いのは生活空間と一体となっているワンルームマンションなどを事務所とする場合です。 この場合は税務署に事前相談をしつつ、なんらかの方法で生活空間と切り分けて、販売場の独立性・区分性を維持する工夫が必要です。
ワインセラー、倉庫
事務所と店舗だけがあっても酒類販売業は成り立たず、ワインであればワインセラー、その他の酒類であっても何らかの倉庫が必要です。 ワインセラー・倉庫が販売場に隣接して一体として機能する場合、販売場の申請の際にワインセラー・倉庫の場所を明示します。 少し離れた場所にワインセラーや倉庫がある場合は、申請の本体とは別に、「蔵置所(ぞうちどころ)設置報告書」を予め提出することを要し、 こちらについても酒類の適正な管理体制を図るために(=在庫を適正に管理するために)、 独立性と区分性は当然に要求されると解されます。 蔵置所では、販売や受発注ができないなど、販売場とは異なる留意点がありますので、別の投稿で詳細に論じたいと思います。
土地の地目
場所的要件を規定する酒税法の第10条9号とは異なる規定ではありますが、 同じ場所に関する要件として、販売場の位置する土地の地目が農地でないことが要件とされます。 申請書の添付書類として、土地が農地の場合は農地転用許可関係書類(写)の添付が要求される他、 土地の登記事項証明書も申請の際の添付書類です。
ブログ記事をご覧いただき、ありがとうございました。 本稿でご紹介したような、自宅マンション、賃貸マンション、シェアオフィスに関する相談も多く、工夫をすれば場所的要件を満たせる場合もあります。 当事務所の相談料は無料です。LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法(第9条 第10条)
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori