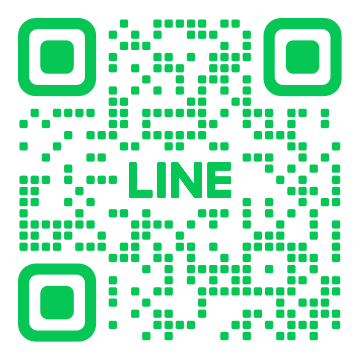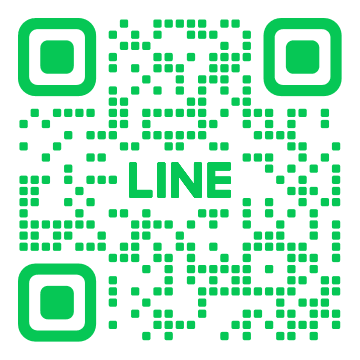一般酒類小売業免許における経営基礎要件
記事を開いていただきありがとうございます。本稿ではワインショップ等の一般酒類小売業免許の4つの要件のうち、 場所的要件と並んで苦労する方が多い経営基礎要件について、J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。

経営基礎要件の根拠条文と背景
経営基礎要件の根拠条文は酒税法10条10項です。下記に引用します。前段の破産手続き開始の決定を受けていないというのは例示であり、後段の「経営の基礎が貧弱であると認められる場合」という部分が要件です。 なお、10条の本文は「次の各号のいずれかに該当するときは免許を与えないことができる」という規定になっているので、10項については「経営の基礎が貧弱であると言えない」あるいは「経営の基礎が十分である」というのが要件になります。
酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
出所:酒税法10条10項
同じお酒業界における許認可である、バーやキャバクラ(風俗1号営業)にはこのような経営基礎要件は求められていないにも関わらず、 ワインショップ等の酒類販売業者に「十分な経営の基礎」が求められる背景には、「酒類免許制度が酒税の適切かつ確実な賦課徴収を図るための制度である※」点と深い関わりがあります。 酒税の納税義務を負うのは生産者ですが、酒税負担は最終的には、酒類販売業者からワイン等酒類を購入する、最終消費者又は飲食店が負担します。 従って、酒類製造業者から、酒類卸売業者、酒類小売業者に至るまで、全ての業者に十分な経営の基礎がないことには、酒税の安定的な確保が図れないということになります。
経営基礎要件の具体的な内容
酒税法10条10号を受けて、国税庁の酒税法の解釈通達が、より具体的な解釈を定めています。下記、酒税法10条10号の解釈通達の本文を、 (製造業免許を除いた)酒類販売業免許に関わる部分に限定し、また、一部括弧書き等を省略しながら読みやすい形で引用します。
「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者等において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的信用の薄弱、製品又は販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいう。 なお、申請者等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、申請者等が次の事項のいずれかに該当する場合又は申請者等が次の2から10に掲げる要件を充足していない場合には、申請者等において、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当するものとして取り扱う。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額 (資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額とする。以下同じ。) を上回っている場合又は最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 申請販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、当該店舗の除却又は移転を命じられている場合
- (製造業に関わる規定につき省略)
- (製造業に関わる規定につき省略)
- 申請酒類小売販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
出所:国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」- 1 「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義
決算書に関わる要件
最もわかりにくい、(3)の前段部分につき、原則、純資産の部が正の金額であれば問題はありません。詳細は別の投稿で論じます。 後段については、過去3期の全ての期において、資本等の額の20%を超える欠損が生じている場合は要件を満たしませんが、 資本等の額の20%を超える欠損が生じている期が、過去3期のうち、1期あるいは2期に留まっている場合は問題になりません。 また、個人の場合は決算書はありませんので、過去3期分の確定申告を通じて(3)の要件が確認されます。

(3)以外では、免許権者が税務署ですので、(1)に記載の通り税金の滞納がある場合は不許可です。 その他、一見すると経営の基礎とは無関係に思える(8) 「酒類の適正な販売管理体制」が経営の基礎要件の一要素とされています。 以上が、卸売業免許も含めた酒類販売免許に求められる経営基礎要件ですが、解釈通達では、 それぞれの免許区分に応じて個別の経営基礎要件を定めています。一般酒類小売業免許については次の通りです。
- (1) 経歴及び経営能力等 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又は これらの者が主体となって組織する法人である。
- (注) 申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、 酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、 独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。
1 酒類の製造業若しくは販売業の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して 経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で 酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 - (2) 販売能力及び所要資金等 申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに 必要な販売施設及び設備を有している者又は所有資金を有し免許を付与するまでに 販売施設及び設備を有することが確実と認められる者である。
出所:国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」- 3 一般酒類小売業免許についての取扱い
経営基礎要件の人的要素
経営基礎要件は、法人及び個人の財産的な基礎だけが審査の対象となるのではなく、申請者あるいは申請法人の役員、支配人の「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有する」か否かも審査されます(経営基礎要件の人的要素)。
3年以上の酒類業界の経営経験があれば問題ないことは明らかです。また、この経験は必ずしも経営者でなくても、酒類業界の経営経験があると認められればいいので、支配人、店長、といった経験でも十分と言われます。難易度が上がるのは、酒類業界の経験とは言い難い職歴の場合、または、酒類業界の経験がある場合でも経営経験とは言い難い経験の場合です。 このような場合は、形式的な申請書を作成しても、税務署は要件の該当性を判断できず不許可となってしまうので、申請者のこれまでのキャリア、経営に準じる経験、酒類業界に関する知識(ソムリエ、ワインエキスパート、酒Diplomaといった資格も有効)を当事務所とその提携事務所又は他の酒類販売を専門とする行政書士が丁寧にヒアリングした上、要件を満たし得ると判断できれば、 税務署に対して、その要件該当性を丁寧に書面で説明し、税務署の要件該当性の判断を助ける求めるという方法をとります。
解説を読んでいただき、ありがとうございました。経営基礎要件の人的要素は悩まれる方も多いと思います。 当事務所では本稿で紹介した経営基礎要件を含む要件該当性の初期的な判断も含めた相談に無料で応じています。私はワインショップを開けるのだろうか?と疑問を持たれている方、 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法(第10条)
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 最二小判平成10・7・3(集民第189号11頁)- 酒類販売業免許申請に対する拒否処分取消
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori