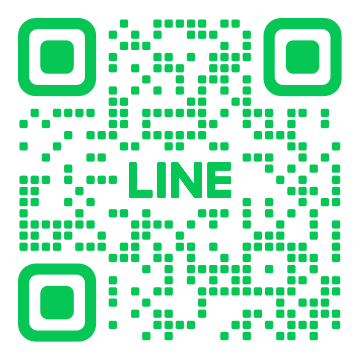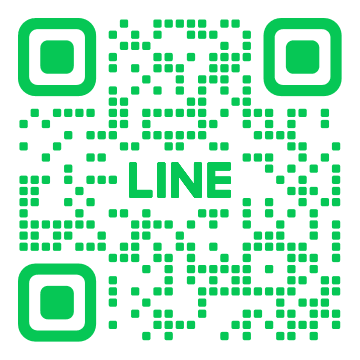「酒類販売管理者」とは?ワインエキスパートを有する行政書士が解説!
ワインショップ等の一般酒類小売業においても、通信販売酒類小売業においても、お酒の小売業を営む際には、小売販売場(各店舗や事務所)ごとに、「酒類販売管理者」を選任する義務があります。 本記事では、酒類販売管理者の業務内容、選任基準、必要な手続きや表示義務、さらには研修の受講についてJ.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が解説いたします。 筆者も、本稿で紹介する酒類販売管理研修を受講しました。

酒類販売管理者とは何か
酒類販売管理者は、各販売場(店舗・事務所)ごとにお酒の適正な販売体制・管理体制を確保するため、管理と指導を担当する責任者です。 酒類小売免許を取得する場合、販売場ごとに必ず1名の酒類販売管理者を配置しなければなりません(ワイナリーや酒類卸売業者であって、酒類販売業者のみを顧客とする場合は不要)。
新たに酒類販売業免許を取得する場合
新たにワインショップ等の酒販店を始める場合、申請者は、酒類の販売業務を開始する時までに「酒類販売管理者」を専任しなければならず、 酒類販売業免許の申請書本体(及び次葉6)に、酒類販売管理者に専任予定の者の氏名を記載します。 下記に申請書本体の一部と次葉6の一部を掲載します。
申請書本体の一部(酒類販売管理者の部分)

酒類の販売管理の方法(次葉6)の一部(酒類販売管理者の部分)

既に免許を取得済みの場合、酒類販売管理者が欠けると営業ができないことに注意が必要です。選任をしないと、50万円以下の罰金です。
酒類販売管理者選任届出署
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に選任届(又は解任届)を届け出なければならないとされます(下記)。 新規に免許を取得するときは、免許の交付時にこの届出書の提出を求められます。よって実務的には、酒類販売免許の申請を検討し始めた段階で(他の要件を満たしていれば)、 すぐに申請者または申請者以外の者で販売場に常駐する予定の者が後述する酒類販売管理研修を受講することをお勧めします。

酒類販売管理者になる方法
酒類販売管理者には誰でもなれる訳ではなく、法律上、一定の要件が定められています。 具体的には、酒類の販売業務に従事する者(新規の場合は従事する予定の者)で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の(1)~(3)の全てに該当する者とされます。 なお、酒類小売業者(法人であるときはその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは(新規の場合は従事する予定のとき)、自ら酒類販売管理者となることができます。
- 次のイ~ハに該当しない者
- イ:未成年者
- ロ:精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- ハ:酒税法第 10 条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
- 酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
- 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
上記の1,2,3を全て満たす場合、酒類販売管理研修を受講すれば、酒類販売管理者となる資格を得ることができます。 1のハにつき、なんらかの酒税法上の免許を取り消されたから3年を経過しない者、一定の刑事罰で有罪となり、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者を指します。
酒類販売管理研修とは
酒類販売管理者研修は私も参加しましたが、3時間ほどの講義で終わります。とくにテストもなく講義さえ聞いていれば受講証がもらえます。 講義の内容は未成年者の飲酒防止に関わる内容など、法令や酒販店開業後の経営や管理に関する内容が多いです。時期によっては混んでいるので、酒類販売免許を申請予定の場合は、 早めに予約することをおすすめします。下記は東京都で酒類販売研修を実施している主な団体です。申込みは国税庁ではなく、各団体のホームページで申込みます。
| 組織名 |
|---|
| 東京小売酒販組合 |
| 東京都卸売酒販組合 |
| 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 |
| 日本チェーンストア協会 |
| 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会 |
| 一般社団法人全国スーパーマーケット協会 |
| 全国小売酒販組合中央会 |
| 一般社団法人酒類政策研究所「酒類販売管理研修事務センター」 |
酒類販売小売業免許においては、経営基礎要件の人的側面において、酒類業界での経営経験や知識が審査の対象とされていますが、 免許の申請時に既に酒類販売管理研修の受講を終えていると、多少のプラスに働くことも期待されます。経営基礎要件の人的側面については、私の下記の記事をご覧ください。
一般酒類小売業免許における経営基礎要件まとめ
解説を読んでいただき、ありがとうございました。 酒類販売免許はわかりにくく、とくに委託製造、OEM販売では悩まれる方も多いと思います。 行政書士事務所Crenlyでは、本稿で紹介した委託製造、OEM販売を含む、 酒類販売業免許の相談に無料で応じています!代表はJ.S.A.ワインエキスパートも有しており、ワインの専門です。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせください! また、ご要望と難易度に応じて、代表と同じくJ.S.A.ワインエキスパートを有する提携先の女性の行政書士と(単独受任時と変わらない価格で)共同受任することも可能です。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「お酒に関する情報」
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori