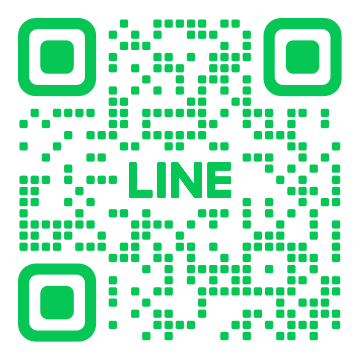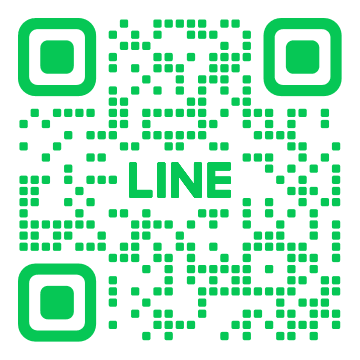角打ち営業は違法か?飲食店でのお酒提供と必要な許可
角打ちとは、従来の飲食店や酒屋の枠組みにとらわれず、酒類の小売と立ち飲みが融合した(その狭間の)独自の営業形態です。 法律上は、飲食店営業許可と酒販店(酒類販売業免許)は明確に区別されており、酒税法上、原則として飲食店では未開栓のワインや日本酒等、お酒の販売はできず、 反対に、酒販店では、店内でお客さんが飲食するためのお酒を提供できません。 本記事では、角打ちの仕組み、適法に営業するために必要な許可と、運営にあたっての注意点について、 J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が解説いたします。

酒類販売業免許と飲食店営業許可の区別
酒税法は、国の重要な税収源である酒類に対し、厳格なルールを定めています。 一般的に、飲食店は「提供」の範囲でアルコールを扱い、ビンや缶を開栓した状態で客に提供します。 一方、酒類の「販売」とは、開封せずにそのまま取引することを意味し、これには「一般酒類小売業免許」が必要です。 飲食店営業許可では開栓をしていない酒類の小売は原則認められておらず(店内飲食用にボトルを入れるのはもちろん可能)、どうしてもお酒を売りたい場合は、 それぞれの営業を物理的に、会計上も在庫も、明確に区分しなければなりません。下記の図の通り、酒販店から見て飲食店は法令上の顧客にあたります。

角打ちの営業形態
角打ちは、店舗内でワイン等お酒の小売りが行われる一方、立ち飲み形式で消費できる仕組みですが、2つの法形態が混在しています。
角打ち営業 - 1.飲食店による酒類販売業免許
1つめは飲食店が角打ち営業をするケースです。具体的には、飲食店の店舗内において飲食店のエリアと酒類販売のエリアを物理的に区分した上で、 ワイン等のお酒のボトルの店内飲食は飲食店のエリアで、ワイン等お酒の持ち帰りでの販売は、酒類販売のエリアで実施します。 物理的なスペースに加えて、それぞれの仕入れ先、在庫、会計を分ける必要がありますが、このスキームで角打ちに近い営業形態が実現できます。 このケースの角打ち営業は、通常の飲食店と同様の飲食業許可に加えて、酒類販売業免許(一般酒類小売業免許)の取得が必要です。
角打ち営業 - 2.イートイン
もう一方の角打ち営業は、ショッピングモールや複数の店舗が入居するビルやフロア(商業施設)において、各店舗の共用の飲食スペースが設置されているケースです。 この場合、ワイン等未開栓のお酒を販売する主体は酒類販売免許(一般酒類小売業免許)を取得し、お酒を販売しているのですが、 このお酒を購入したお客さんは、同酒販店とは全く別の営業主体であるショッピングモールや店舗の共用エリアでそのお酒を自分で飲んでいるため、 本節の冒頭で紹介したような営業の物理的区分、会計の区分、在庫の区分の要件が満たされることになります。 このスタイルの角打ち営業は、ショッピンモール等商業施設の企画・設計段階から税務署とも相談しながら設計を進める必要があるため、 小規模の酒販店や飲食店ではななかなか、実現が難しいかもしれません。 なお酒販店が、隣接する場所に(飲食店ではなく)自らイートインスペースを設置する角打ち営業のケースは、別の運営主体である場合と比べて、法令上のハードルがあがりますので、事前に酒類販売を専門とする行政書士への相談をお勧めします。
3.試飲
角打ち営業と似た営業スタイルに、酒販店における試飲があります。これはボトルを販売している酒販店の店内で、飲食店のようなテーブルと椅子で飲食をするのではなく、 あくまで紙コップ、場合によってはグラスによって試飲をする形態です。ワインショップでの酒類販売免許による、試飲スペースの設置は、飲食店営業と紙一重の部分がありますので、行政書士と税務署には事前相談が必要です。
角打ちの営業の許可と留意点
前述の3つの角打ち営業のスタイルのうち、2と3は、税務署への慎重な事前を要するもの、酒類販売免許のみによって実現が可能です。 ここでは飲食店による酒類販売業免許の留意点について述べたいと思います。
- 物理的なスペースの分割
飲食店と酒類販売のエリアを空間的に分離し、双方が混在しないようにすることが求められます。 ドアによって区分されていることが理想的ですが、壁やその他仕切りによって明確に両者が区分されていれば、必ずしもドアは不可欠ではありません。 - 会計・伝票の明確な区分
酒類の売上と飲食の売上が同じレジで処理されると、酒類販売免許(一般酒類小売業免許)の申請時に不備・不許可となるため、飲食店と酒販店は、レジと伝票も別々に管理する必要があります。 - 仕入れ先・ワインセラーの分離
飲食店の在庫と酒販店のワイン等お酒の在庫は明確に区別し、それぞれの仕入れ先を別に確保することが重要です。 飲食店が一般酒類小売業免許を取得するケースでは、ボトルで販売するお酒は、従来飲食店で利用していた仕入れ先ではなく、卸売業免許を持つ酒販店から仕入れる必要があります。 加えて、仕入れを終えた後の保管においても両者の在庫が混在しないよう、例えばワインのあれば、それぞれで別のワインセラーを用意する必要があります。
酒類販売免許そのものの要件やポイントは、私の下記の酒類販売免許の関連記事一覧からご確認ください。
酒類販売免許の関連記事まとめ
解説を読んでいただき、ありがとうございました。 酒類販売免許はわかりにくく、とくに飲食店と併設のケースでは悩まれる方も多いと思います。 行政書士事務所Crenlyでは、本稿で紹介した角打ち営業を含む、 酒類販売業免許の相談に無料で応じています!代表はJ.S.A.ワインエキスパートも有しており、ワインの専門です。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせください! また、ご要望と難易度に応じて、代表と同じくJ.S.A.ワインエキスパートを有する提携先の女性の行政書士と(単独受任時と変わらない価格で)共同受任することも可能です。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
- 国税庁「お酒に関する情報」
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori