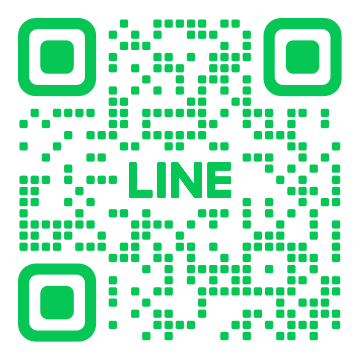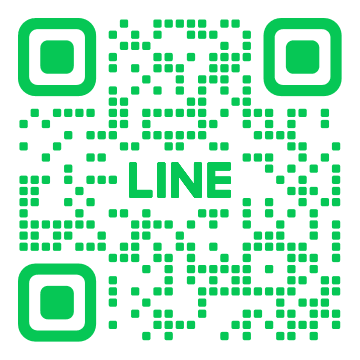酒類業界の構造と酒税法上の免許区分
ブログをご覧いただきありがとうございます。本稿では、酒類業界の構造と酒税法上の免許区分について、J.S.A. ワインエキスパートで行政書士の筆者が整理・考察いたします。

酒類業界の流通構造と「卸」の考え方
上の画像では、酒類メーカー、卸業者(いわゆる問屋)、酒販店、飲食店、一般消費者といった構造が示されています。 一般に「飲食店にお酒を売る=卸」と思われがちですが、酒税法上の「卸免許」は、あくまで酒販店へ酒類を卸す業態を指します。
- 税法上の卸業者:メーカーから酒類を仕入れ、酒販店に販売
- 税法上の小売業:卸業者から仕入れ、消費者や飲食店に販売
一般に、飲食店へ酒類を販売する事業者は「卸業者」という印象があります。 しかし酒税法上、「卸免許」と呼ばれる免許区分は、酒販店などの業者向けに卸売を行う形態を指します。 飲食店はあくまでも最終的にお酒を提供する立場にあるため、「飲食店向けにお酒を卸す」ことは、税法上は小売業免許(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許)で行います。
「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の違い
「一般酒類小売業免許」は、消費者に対して酒類を販売し、または飲食店に対して酒類を提供するために必要な免許です。 後述の「通信販売修理小売業免許」とは異なり、全ての品目の酒類を小売できる点が特徴です。実店舗での販売が想定された免許区分ですが、実店舗を持たずに事務所だけの販売も可能です。販売地域が店舗近隣か、単一の都道府県内に限定される場合などは、こちらの免許を検討します。 販売先が単一の都道府県に限定されている限りは、チラシによる販売など、一般的には、通信販売と言えるような方法で酒類を販売しても構いません。
一方、「通信販売酒類小売業免許」は、インターネット、電話、チラシなどで酒類を受注して、配送するビジネスモデル向けの免許ですが、 都道府県をまたいだ受注と販売が可能である点が最大の特徴です。都道府県をまたぐ場合は、原則としてこちらの免許区分が必要となります。 ただし、自己の販売場の近隣エリア(商圏)であれば、複数都道府県にわたる受注販売であっても一般酒類小売業免許で対応できる場合もありますが、このケースでは税務署への事前相談が不可欠です。
通信販売酒類小売業免許で取り扱える国産酒類は「課税移出数量3,000キロリットル未満」の酒類に限定されます。従って、国産酒類を取扱う場合は、 生産者から課税移出数量が3,000キロリットル未満である証明書を取得する必要があります。輸入酒の場合は、このような制限はありません。
両者の違いについては、下記の記事でより詳細に書いていますので、必要に応じてご覧頂ければ幸いです。
まとめ
「卸」という呼称の誤解
飲食店への酒類販売が必ずしも「卸免許」ではないことに留意が必要です。酒税法上の「卸免許」は、あくまで業者間取引を想定しています。
小売業免許は2種類
一般消費者や飲食店に対する販売を行う場合は、一般酒類小売業免許、または、通信販売酒類小売業免許を検討します。取扱う酒類、販売形態、販売地域によって必要な免許が異なります。
ブログ記事をご覧いただき、ありがとうございました。酒類業界の構造や免許区分は複雑に見えますが、実際のビジネス形態や販売対象を整理することで、必要となる免許や許可が明確になります。 当事務所の相談料は無料です。LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
藤原先生でも古森でも、どちらに頼んでも、両方に頼んでも、同じ報酬で事業者を全力サポート、相談料無料!
参考法令・資料
- 酒税法(第9条、第10条)
- 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」
- 国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」令和5年7月改訂版
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori