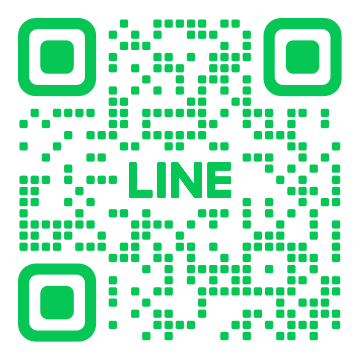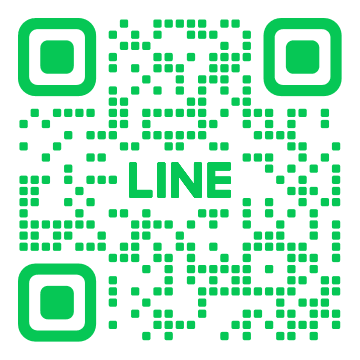2025年 中小企業省力化投資補助金(一般型) - 申請の要件、対象経費、スケジュールを行政書士が解説!
2025年1月28日に公募要領が発表され、2025年3月19日から、2025年の「中小企業省力化投資補助金(うち一般型)」の応募申請受付が開始されました。 中小企業省力化投資補助金(通称、省力化補助金)は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、 人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援し、 これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。 本稿では、銀行への勤務経験もある行政書士が、「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の申請の要件、対象経費、スケジュールについて解説いたします!

中小企業省力化投資補助金(一般型)のスケジュール
本稿は「一般型」について説明しますが、「中小企業成長加速化補助金」には、「一般型」の他にも「カタログ注文型」があります。 「カタログ注文型」は事前に登録・掲載されたリストから製品を選びます。 それに対して、2025年から新設の「一般型」では、(カタログがなく)、オーダーメイドの設備やシステムも対象になりました。 「カタログ型」については別の記事で詳細に説明したいと思います。
「一般型」のスケジュール
「一般型」は2025年から新設され、年に3~4回の公募が実施されるとが公開されています。 公募開始日、公募締切日、採択発表日が定まっていることが特徴です。小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金を始めとした多くの補助金と同様のプロセスです。 なお、申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。また審査は、書面審査と口頭審査の2段階です。

補助率と補助上限額
下記が一般型の補助率と補助上限額です。 中小企業では補助率は1/2で一定ですが、中小企業より規模の小さい小規模企業者・小規模事業者(個人事業者を含む)では、 補助率が2/3に引きあがります。小規模事業者の定義は下段の表を確認ください。 その他、従業員数によっても、補助上限額が大きく異なる点が、中小企業省力化投資補助金の特徴です。 大幅な賃上げは、事業終了時に①給与支給総額を6%以上、かつ②事業場最低賃金+45円以上とする計画を策定する必要があります。
| 従業員数 | 補助率※ | 補助上限額 | 大幅な賃上げを行う場合 |
|---|---|---|---|
| 5名以下 | 中小企業 1/2 小規模・再生 2/3 | 750万円 | 1,000万円 |
| 6~20名 | 1,500万円 | 2,000万円 | |
| 21~50名 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
| 51~100名 | 4,000万円 | 6,500万円 | |
| 101名以上 | 5,000万円 / 8,000万円 | 6,500万円 / 1億円 |
小規模事業者の定義
| 業種 | 常時従業員数 |
|---|---|
| 製造業その他 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
| 商業・サービス業 | 5人以下の会社及び個人事業主 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
要件
要件は4つあり、賃上げが極めて重視されていることがわかります。 また従来の「カタログ型」は1番目の要件が3%以上とされていましたが、「一般型」では1番目の要件が4%以上に引きあがっています。
- 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
- 1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の 年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
- 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ) み)
2番目と3番目の要件は比較的わかりやすいので、1番目と4番目の要件について補足します。なお、2番目と3番目の要件が未達成の場合には、達成度(未達成度)に応じて補助金を返還する義務があります。
1.労働生産性の考え方
付加価値は「営業利益+人件費+減価償却費」で、労働生産性はこの付加価値を従業員数(役員を含む)で割ったものです。 申請前での直近決算値と報告時(カタログ注文型は3年間、一般型は5年間)の値を比較して、3%あるいは5%の労働生産性の向上を続ける必要があります。 人件費、減価償却費、従業員数の計画は立てやすいので、最も重要な項目は営業利益になります。営業利益が上昇基調にあるタイミングでの申請が重要と言えます。
4.一般事業主行動計画とは
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。 従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられていますが、中小企業成長加速化補助金の申請では授業員が21名以上の場合に、作成と公表が要件とされています。
補助対象経費
さて、「一般型」は経費オーダーメイド性のある多様な設備やシステムを導入可能とされていますが、具体的な補助対象経費は次の通りです。
- 機械装置・システム構築費(必須)
これは必須です。機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費と、専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費、 及び、それらの改良又は据付けに要する経費が対象とされます。また、必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要です。 - 技術導入費
知的財産権等の導入に要する経費です。補助対象経費総額(税抜)の3分の1が上限です。 - 知的財産権等関連経費
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等です。補助対象経費総額(税抜)の3分の1が上限です。 - 専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費です。補助対象経費総額(税抜)の2分の1が上限です。 - 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費です。 - クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費です。 - 外注費
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費です。 補助対象経費総額(税抜)の2分の1が上限です。
「一般型」の申請スケジュール
2025年の「一般型」の申請スケジュールは次の通りです。2025年3月30日時点では、第1回公募回しか公開されておりませんが、 今後公表がされ次第本稿もアップデートします。「カタログ型」については前述の通り随時申請が可能です。
| 公募回 | 公募開始日 | 公募締切日 | 採択発表日 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2025年1月30日(木) | 2025年3月31日(月)17:00 | 2025年6月中旬(予定) |
事業計画
申請書類(添付書類)は多いですが、最後にその中でも審査において最も重要な事業計画について説明します。 事業計画書には、補助事業の目的や取組内容、労働生産性向上目標の達成手段を具体的かつ詳細に記載します。 自社の現状や課題、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、なぜ機械装置等の導入が必要なのかを明確にし、具体的な工程を示しながら、それらがどのように労働生産性の向上に結びつくのかを示す必要があります。
定量化の整合性
投資がどのように業務の省力化・効率化・労働生産性の向上に寄与するのか、例えば省力化指数や投資回収期間などの数値目標およびその算出根拠を提示しながら、全社の事業計画との整合性を説明することが求められます。 また、補助事業の実施により得られる将来的な付加価値や労働力の再配置などのシナジー効果についても、図表や具体例を用いて詳細に記載し、計画の実現可能性と信頼性を裏付けることが重要です。
賃上げ
加えて、事業計画書には具体的な賃上げの数値目標(例:一人当たり給与支給総額や全社の給与支給総額の増加率)とその算出根拠を明確に示す必要があります。 賃上げが一時的な措置ではなく、企業全体の成長戦略と連動し、継続的に実施される計画であることを証明するため、計画実施のスケジュールや体制、設備投資や人材育成などの連携施策も詳細に記述することが求められます。 その他、別の記事で詳細を論じたいと思いますが、本補助金には他の補助金同様の加点項目もあり、加点を得ることも採択にはとても重要です。
まとめ
「中小企業省力化投資補助金」は、最大で1億円の補助が見込める大型の補助金である一方、本稿で紹介したような要件と多くの書類審査・口頭審査があり、そららを満たす 事業計画とプレゼンテーションを作成する必要があります。また、金融機関(銀行)の理解と後押しも必要です。 筆者は、銀行勤務経験(法人営業)を有する行政書士として、中小企業の皆様の「中小企業省力化投資補助金」 の相談と申請支援に応じています。 加えて当事務では、中小企業の皆様により上質なサービスを提供すべく 当事務所代表と同様の知識と経験を有する行政書士とともに、単独受任時と変わらない報酬での共同受任にも応じています。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
提携先:行政書士藤原七海事務所
参考法令・資料
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業省力化投資補助金公式サイト
- 2025年 中小企業省力化投資補助金 公募要領
本稿の筆者

行政書士
東京都行政書士会所属
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori